高学年になると、勉強に対する姿勢が変わる子どもが多くなります。それは成長の一環ですが、親としてはどう対応すべきか悩むところです。この記事では、子どもが勉強しない理由や効果的な声掛け術を詳しく解説します。これで親のイライラも軽減され、子どもの自主性がぐんと上がること間違いなしです!
高学年が勉強しない理由はココにあった!
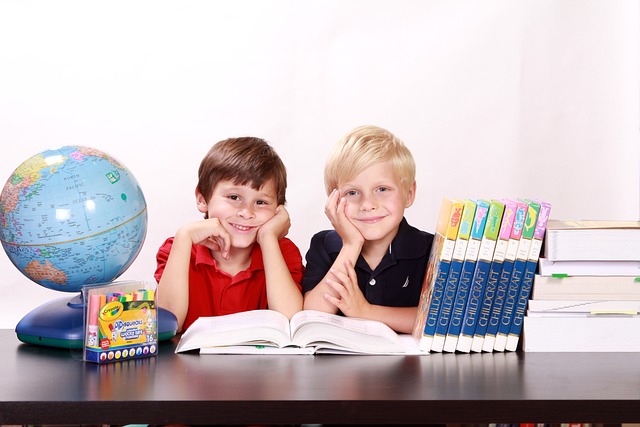
「うちの子、低学年の頃はあんなに勉強好きだったのに…」と、高学年になってからのお子さんの変化に戸惑っていませんか?実は、高学年になると、精神的に大きく成長する一方で、勉強に対する意識も変化する時期なんです。
例えば、高学年になると、友達との関係性が複雑化し、友達と過ごす時間の楽しさに気付き始めます。「遊びと勉強、どっちが大切なの!?」なんて、心の中で葛藤している子もいるかもしれません。
また、学習内容が難しくなり、努力しても結果が出ないと「どうせ頑張っても無駄だ…」と、勉強へのやる気をなくしてしまうことも。高学年になると、今までのように「褒められたい」「親を喜ばせたい」という気持ちだけでは、勉強へのモチベーションを維持するのが難しくなるのです。
さらに、自我が芽生え、親にあれこれ言われることを嫌がるように…。「勉強しなさい!」と口うるさく言うほど、「うるさいな」「放っておいてよ」と、子どもの反発心をかってしまう可能性もあります。
高学年ならではの勉強しない理由は?
- 友達との時間の方が楽しくなる:友達との関係性が深まり、遊びや会話など、学校外の交流が増えることで、相対的に勉強の優先順位が下がってしまう。
- 学習内容の難化による自信喪失:今までのように簡単に理解できず、努力しても結果に結びつかないことで、勉強への意欲や自信を失ってしまう。
- 自我の芽生えと親からの干渉:自分の意見や考えを持つようになり、親からの指示や命令に反発しやすくなる。
このように、高学年になると、今までとは異なる理由で勉強から遠ざかってしまうケースが見られます。
次の章では、これらの原因を踏まえ、子どものやる気を引き出すための具体的な対処法を5つご紹介します。
子どものやる気を引き出す対処法5選
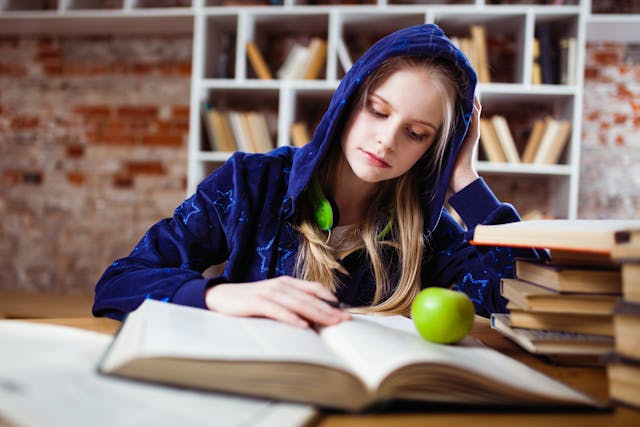
「勉強しなさい!」とガミガミ言うのは逆効果。では、具体的にどうすればいいのでしょうか?ここでは、高学年の子どものやる気を引き出す対処法を5つご紹介します。
- 目標を共有する
漠然と「勉強しなさい」と言うのではなく、「次のテストで〇〇点目指そう!」と、具体的な目標を一緒に設定してみましょう。目標を達成したら、一緒に祝うことも忘れずに! - 成功体験を積み重ねる
最初から難しい問題に挑戦するのではなく、まずは簡単な問題から始め、小さな成功体験を積み重ねることで、自信をつけさせてあげましょう。「この前より解けるようになってるじゃん!すごいね!」と、具体的に褒めてあげることがポイントです。 - 学習環境を整える
勉強に集中しやすい環境作りも大切です。リビング学習は、親の目があって安心できる反面、テレビや周りの音に気を取られやすいというデメリットも。子ども部屋に机を置くスペースがない場合は、リビングの一角に勉強スペースを作ってあげましょう。 - 勉強のメリットを伝える
「なんで勉強しないといけないの?」という子どもの疑問に、真正面から向き合ってみましょう。例えば、「将来、〇〇になりたいんだよね?そのためには、こんな勉強が必要なんだよ」と、夢と結びつけて伝えることで、子どもは勉強の必要性を実感しやすくなります。 - ゲーム感覚を取り入れる
「勉強=つまらないもの」というイメージを払拭するために、ゲーム感覚で学習できるアプリや教材を活用するのもおすすめです。楽しく学習できるだけでなく、子どもの学習進度に合わせて問題の難易度を調整してくれるので、無理なく学習習慣を身につけることができます。
イライラしない声掛けのコツはここが違う

反抗期に突入した高学年の子どもに、頭ごなしに「勉強しなさい!」と言っても、反発されるのがオチ。「また怒られる…」と、子どもを萎縮させてしまう前に、声掛けのコツを押さえておきましょう。
例えば、「早く勉強しなさい!」ではなく、「あと30分したら、ご飯だから、それまでに宿題終わらせようか」と、具体的に伝えるように意識してみましょう。子どもは、時間に余裕がないと焦ってしまい、余計にやる気をなくしてしまいます。
また、「なんで勉強しないの!」と頭ごなしに叱るのではなく、「今日は、何の教科の勉強をする予定?」と、子どもの意思を確認する声掛けを心がけましょう。
高学年の子どもへの効果的な声かけ例
「早く勉強しなさい!」ではなく…
「あと30分でご飯だから、それまでに宿題終わらせようか」
「タイマーを1時間セットして、集中してやってみよう!」
「なんで勉強しないの!」ではなく…
「今日は、何の教科の勉強をする予定?」
「何か困っていることあったら、教えてね」
ポイントは、頭ごなしに命令するのではなく、子どもの気持ちを尊重し、自主性を促すような声かけをすること。「勉強しなさい!」と言われると、子どもは「勉強させられている」と感じてしまいます。しかし、「あと〇分でご飯だよ」と伝えると、子どもは自分で時間を意識し、行動に移せるようになるのです。
また、「今日はどの教科を勉強したい気分?」と尋ねることで、子どもは「自分で決めた」という意識を持つことができます。
声かけ一つで、子どものやる気は大きく変わります。親のイライラを減らし、子どもとのコミュニケーションを円滑にするためにも、ぜひこれらの声かけを試してみてください。
親子関係を壊さない高学年対応の秘訣

思春期に突入する高学年は、親の言うことを素直に聞けなくなる時期。そこで、子どもの自主性を尊重しながら、学習習慣を身につけるための秘訣をご紹介します。
まず、大切なのは、過度な干渉は控えること。子ども部屋にこもりきりになったとしても、常に監視したり、逐一「勉強は終わったの?」と口出ししたりするのはNGです。
高学年の子どもへの接し方のポイント
「見守る」姿勢を大切にする:常に監視するのではなく、遠くから温かく見守る姿勢が大切。
「信頼している」ことを伝える:「あなたは一人でできる」と信じていることを言葉や態度で示す。
「相談しやすい雰囲気」を作る:困ったことがあったら、いつでも相談しやすい雰囲気作りを心がける。
思春期を迎えると、子どもは親離れを始め、自分の力で物事を解決しようとするようになります。そこで、親は「いつでもサポートする」という姿勢を見せつつ、子どもの自主性を尊重することが重要です。
例えば、テストの結果が悪かったとしても、「なんでこんな点数なの!」と責めるのではなく、「次はどうすればいいと思う?」と、子ども自身に考えさせるように促してみましょう。
「何か困ったことがあったら、いつでも相談してね」と、いつでも頼れる存在であることを伝え、子どもとの信頼関係を築くことを意識しましょう。
親が過度に干渉せず、子どもの自主性を尊重することで、子どもは自分自身の力で成長していくことができます。
忙しいワーママ必読!週末リカバリー学習術

「平日は仕事で忙しくて、子どもの勉強を見てあげられない…」と、悩んでいるワーママも多いのではないでしょうか。 週末は家事や家族の時間に追われて、ゆっくり勉強を見てあげられない… という声も聞こえてきそうです。
ここでは週末の短時間でも効果的な学習方法、「週末リカバリー学習術」をご紹介します。ポイントは、平日にできなかった部分を週末に詰め込むのではなく、1週間の学習内容を「ゆるく」復習すること。
「よし!復習するぞ!」と意気込むと、子どもも身構えてしまいますよね。週末は、あくまで「親子で楽しく」をモットーに、軽い気持ちで復習に取り組みましょう。
週末の午前中は「ゆる復習タイム」: 学校で習った内容を軽く思い出しながら、間違えた問題を1~2問解き直してみる。ノートをパラパラめくって、重要そうなポイントを確認するだけでもOK!
親も一緒に「ながら学習」:子どもが勉強している横で、家事をしながら一緒に問題を解いてみたり、教科書を眺めてみるのも効果的!「お母さんも一緒に勉強する!」と、子どもも喜んでくれるかもしれません。
週末の午後は「気分転換&興味関心を広げる」: 図書館で漫画や小説を借りて、親子で読書タイムを楽しむのもおすすめ。動物園や博物館に出かけて、五感を刺激するのも良いですね。
平日に十分な学習時間が確保できない場合は、週末に「1週間の学びをゆるく振り返る」ことを意識してみましょう。
週末は完璧を求めず、親子で楽しく学び、充実した時間を過ごしましょう。
まとめ
今回は、高学年の子どもが勉強しない理由と、その対処法について解説しました。この記事を読んだあなたは、「うちの子、反抗期だから…」と諦めるのではなく、「子どもの心に寄り添って、対話を重ねていこう!」と、前向きな気持ちになれたのではないでしょうか?親子で笑顔になれる学習習慣を一緒に作っていきましょう!
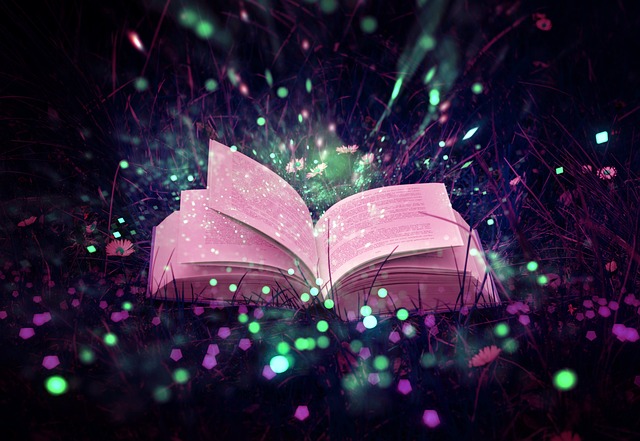


コメント